「へうげもの」15巻が7月23日発売されました。

早いもので「へうげもの」1巻が出版されてから6年半経ちました。
1巻を読んだとき、「こんな戦国時代の描き方があったんだ!」と
衝撃を受けたのを思い出します。
茶人「古田織部」を主人公に戦国時代を文化面から描いていたからです。
巻数が進むにつれ、茶の湯だけにあらず、絵画、陶器から、建築、食に至るまで
戦国時代の最先端の文化が生まれるエピソードが描かれていきます。
そんな文化面の話から歴史的大事件まで
各登場人物の野望とロマンと笑いを交えて、大げさに大げさに話は進んでいくのです。
話はギャグ調で仮説ながら納得いく話になっています。
私が知識不足のためか、どこからが定説でどこまでが仮説なのか分からない話もありますが
毎回、この漫画のへうげた解釈に感心したり、感動したり、ときに笑ってしまうのです。
15巻は、関が原の戦い集結編。
合戦時の家康がテンションおかしすぎて笑ってしまいました。
ハイライトは三成の死に際の名言「柿はたんのどくなのでいらない」の解釈(仮説)でしょう。
毎度のことよく出来た話と感心してしまいましたが、なんとなくしっくりこない。
戦国時代の有名な逸話に織部を無理やり絡ませる解釈がどうも違和感があるんですよね。
ギャグに徹している話は、笑いながら「にんまり」と納得できるんですが・・・。
千利休が切腹した9巻以降どうも仮説の説得力が弱いように思えます。
利休死後、利休の役割を織部になぞり過ぎているように思えてなりません。
9巻までは歴史的事件の裏で利休が暗躍した仮説が取られています。
非常に面白い解釈で、だからこそ利休切腹の謎も納得のいく、
素晴らしい話となったのですが、
織部が毎回のように裏で歴史を動かしていたかのような話では
フィクションとは分かっていても違和感があるのです。
今後、織部を暗躍させるならギャグに徹して欲しいですね。

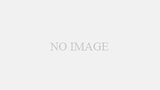

コメントを投稿するにはログインしてください。